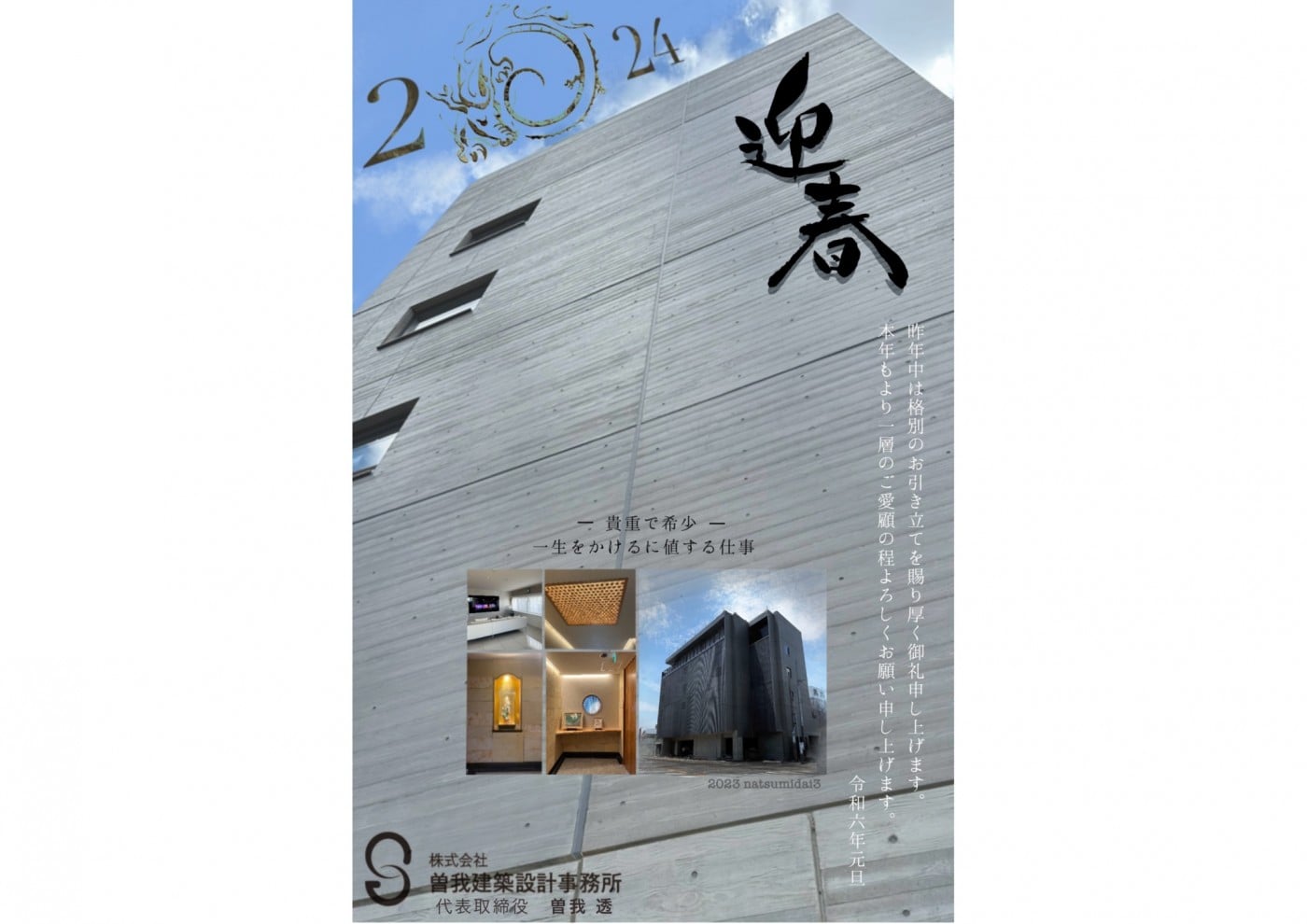ブログ
2月1日 江東区深川2丁目 プロジェクト竣工
2024-02-01
江東区深川2丁目 プロジェクトが先日竣工致しました。
Instagramに動画をアップしましたので、是非御覧ください。
-社員募集中で多くの応募者を見て、「建築・ものづくり の危機感」を感じています-
2024-01-25
-社員募集中で多くの応募者を見て、「建築・ものづくり の危機感」を感じています-
自分が若い頃は、キャリア的にも設計事務所のポジション的にも低くて、まだ若造なので、毎日単純な作業ばかりでした。
たとえば仕上表の線引とか展開図とか天井伏図とか。
一番多く作図させられたのは立面図のタイルの線引でした。
一日中1ミリの水平線を描いたものです。
結婚を機に(30代になり)転職したスターツでは、設計のほとんど全てを任せてもらえるという、今までとは信じられない世界がありました。
バブルのお陰です。
皆さん忙しすぎて、他人の仕事の事など構っていられない状況でした。
それまでの単純な図面作成のみで我慢してきたデザインの世界から、実際に私が作成した図面を基に工事がなされていく。
本当の、現実の建築デザインの世界の醍醐味を経験することが出来ました。
初めて現場監督と打ち合わせをし、下職の大工さん・建具屋さん達と打ち合わせをしていると、そのものづくりのリアルな感覚が自分の進むべき建築家人生を覚醒させてくれました。
下職の気持ちが解らないと「いい建築は出来ない」と大昔に先輩からなんとなく教わっていた記憶が、まさしく本当の事だと確信できました。
私のアプローチ(解決方法)は、ひたすら彼らと酒を酌み交わす事でした。
低レベルの脳では、それくらいしか方法が思い浮かびませんでした。
ほぼ毎日がそういう打ち合わせの日々でした。土曜日曜関係なく。
現場事務所で酒を呑みながら、よく建築の収まりについて語った記憶があります。
数十年後、その中の一人(大工さん)から聞きました。
あの時の私は楽しそうで輝いていて、若さっていいなぁ、と感じさせてくれたそうです。
大切な事は、自分一人で建築を作る事は不可能で、優秀な現場監督始め、その下にいかに優秀な人達(下職)らがいてくれるのか?で「ものづくりの善し悪し」が決まる、ということです。
作品の完成度はそのほとんど全てが人の能力に寄りかかって決定します。
その関係者全員での協奏曲が建築だということです。自分は指揮者です。
ものづくりの基本は、いかに楽しみながら多くの人との関係性を築けるかではないでしょうか?
「建築とは関係づけること」
一年前に亡くなった磯崎新の言葉。昔、ブログでも書き込みました。
2024年度労働基準法改正で、36協定とか、深夜残業とか、有給とか、意識がそこにいってしまう体質では「いい建築・ものづくり」は難しい。
建築は単なる物では無く、社会総合芸術と言われる側面もあります。
手間暇のかかる、世界に一つだけの一品生産。それが建築の本来あるべき姿。
改正労働基準法のせいで、おかしくなってきている大手の施工会社が増えています。
信じられない施工不良、データ改ざんが連続しています。
まず、竣工が遅れるのが当たり前になってしまっています。
理由はいつも「人がいない」です。
しかし、ちゃんと間に合わせる施工会社もあります。
小回りのきく小規模な会社の方がしっかりした仕事が出来ます。
大手企業のように、現場監督が18:00に帰ってしまっては、下職が本気モードで工事ができるわけがありません。
現場監督の能力も非常に問題です。
優秀な監督はヘッドハンティングされて引き抜かれていきます。
そして能力の低い監督だけが残るという悲しい現実。
設計というものづくりの風上にいると、風下の状態がよく見えます。
日本のものづくりがダメになっていく姿がまじまじと見えます。
大げさに表現すれば、国力の低下です。
ではどうしたら良いのか?
今こそ、小企業はそこに勝機があると思います。
簡単です。
「好きこそものの上手なり、その道に入らんと思う志こそ我が身ながらの師匠なりけり。」
すでに450年も前に千利休が言ってました。
画家や彫刻家に労働の意識はきっと無いはずです。
好きもの集団の小規模チーム(会社)にこそチャンスだと思います。
今リクルートで社員募集中ですが、いかに生き方に彷徨っている若い人、見つけられていない若い人の多いことか!
試験勉強をいくらしても生き方の答え、人生の背骨は作れません。
本音と建前。勝ち組と負け組。
ますます分断が明確になってきている現実社会で、自分の居場所を獲得することは難しいかもしれませんが、解決するのは自分の意識改革です。
映画パーフェクト・デイズの役所さんの生き方も悪くはありませんが、若い人はもっと意欲的に、より深く、夢大き生き方をお勧めします。
1月19日 江東区古石場2丁目 プロジェクト竣工
2024-01-19
江東区古石場2丁目 プロジェクトが先日竣工致しました。
Instagramに動画をアップしましたので、是非御覧ください。
1月15日 J Blanc三ノ輪 プロジェクト竣工
2024-01-15
J Blanc三ノ輪が先日竣工致しました。
Instagramに動画をアップしましたので、是非御覧ください。
- 2023 今年を振り返り -
2023-12-28
-2023-今年を振り返り-
久しぶりの更新です。
本当に筆不精になったものです。
帝国データバンク様より、ブログ更新も評価基準になりますよと、脅しを受けてもなお、更新できませんでした。
原因はまさに、健康上の理由です。
今年1月中頃、私自身がまずコロナに感染してしまいました。
おかげで、自宅療養生中だったため、テレビでWBCは全試合観戦できました。
その後、夏見台PJでかなり時間を取られました。
最上階オ-ナールーム付きの本社ビルとなると、それ相応の努力を必要とします。
良い作品にはなったものの、施工会社の人材不足で、引き渡しがだいぶ遅れてしまい、後味の悪い作品になってしまいました。
その後夏頃から、手にしびれを感じ始め、8月のある日、突如目が覚めると激痛に襲われました。
ちょうど発症した日が、バリ島にいたときだったので、最悪の海外渡航でした。
2年連続の不幸なバリ島生活でした。昨年は風邪で、今年はヘルニア。
どうやっても、どういう姿勢でも痛い。なった人にしかわからないものです。
何度も船橋整形外科に通いました。頸椎ヘルニアでした。
最近ようやく回復してきましたが、まだリハビリは必要です。
コロナ禍で還暦を迎え、すべてのお祝い会がなくなり、今年は本格的に忘年会がぎっしりつまり、2019年末とまったく同じ状態にもどりました。
むしろ約4年前以上に食事会が増え、お店の予約が取れない、帰りのタクシーが捕まらない。
まるで、コロナ時代って本当にあったのか?と疑問さえ残ります。
精神面でもこの約4年間で失ったものがあまりに多い。
デザインに必要な 好奇心、向上心が失せてしまいました。
デザインの基礎はコツコツと積み重ねることが重要です。
そしてある日、一瞬でコツをつかむ、階段を駆け上がることができる。
このままで、これで、本当にいいのだろうか? 疑問が残る。
昭和世代にとって、受け継いでいかせなければならない感性があると、ひそかに思っている。
その課題を残しつつ、また新たな年を迎えます。
仕事面では1月30日にユービーエムが倒産し、未回収金が発生し、多少苦労しましたが、リーマンショックや東日本大震災を経験したおかげか?さほどショックは大きくはなかった。
仕事量的にはむしろ逆でした。コロナ禍の影響か?
団塊の世代がいなくなり、代わりに業務を受けてくれる事務所が少なくなってきて、若いメンバーだけで構成されてる当社を選んでくださるお客様が増えました。
その後、順調に推移して、業績も向上しました。
また1月に元スターツの営業社員も入社してくれて、設計営業活動も盛んになり、本格的に総合設計事務所に近付きつつあります。
社員が増えて固定費が増えていく不安より、いまこそチャンス!と、伸びしろの大きさに夢を抱く年の瀬になりました。
来年はさらに、前に一歩です。確実に。
2023/12/28 曽我 透